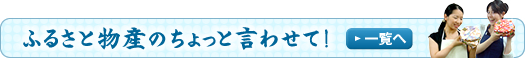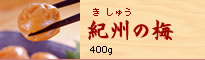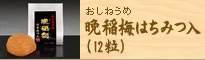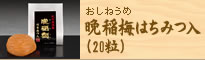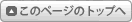梅の歴史2(奈良時代〜戦国時代)
観賞用として愛され、薬としても重宝された梅
美しい梅の花は、昔から人々の心をとらえてきました。また、梅干しは戦国時代に万病の妙薬として重宝されたと言われています。
今回は、それぞれの時代の「梅」と「人」のエピソードをご紹介します。
奈良時代〜平安時代
○ 観賞用として愛された梅の花
奈良時代、「菓子」というと「果物」のことを指していました。梅は梨や桃などと同じように、生菓子として食べられていたそうです。
また、美しい梅の花は人々に大変愛され、平安時代になると公家たちが庭に植えさせて庭木として観賞するようになりました。「花見」といえば、桜を思い浮かべますが、奈良時代から平安時代にかけての頃までは、桜より梅の方が好まれたようです。「万葉集」には、梅を詠んだ歌が118首あり、桜を詠んだ40首よりも多く記されています。
また、美しい梅の花は人々に大変愛され、平安時代になると公家たちが庭に植えさせて庭木として観賞するようになりました。「花見」といえば、桜を思い浮かべますが、奈良時代から平安時代にかけての頃までは、桜より梅の方が好まれたようです。「万葉集」には、梅を詠んだ歌が118首あり、桜を詠んだ40首よりも多く記されています。

これは、拾遺和歌集にある菅原道真の短歌です。
東からの風が吹いたら、それにのせて梅の香りを届けておくれ。あるじの自分がいなくても春を忘れないでおくれ。という意味です。
東からの風が吹いたら、それにのせて梅の香りを届けておくれ。あるじの自分がいなくても春を忘れないでおくれ。という意味です。
○ 平安時代には梅干しが作られていた
平安時代には「梅干し」があったと考えられる文献が残っています。
村上天皇が梅干しとコブ入り茶で病が回復されたと、平安時代の中期の書物に記載されています。現存する最古の医学書「医心方(いしんほう)」にも、梅干しの効用として、熱さまし、吐き気止め、口の乾き止め、下痢止めなどがあげられています。
村上天皇が梅干しとコブ入り茶で病が回復されたと、平安時代の中期の書物に記載されています。現存する最古の医学書「医心方(いしんほう)」にも、梅干しの効用として、熱さまし、吐き気止め、口の乾き止め、下痢止めなどがあげられています。
戦国時代
○ 戦場で活躍した梅干丸(うめぼしがん)
戦国時代に入ると梅干しは広く普及します。
戦場で倒れたときや元気を失ったときなどに唾液を催させる「息合の薬(いきあいぐすり)」として使われました。 戦国時代の武士は、食糧袋に「梅干丸(うめぼしがん)」を常に携帯していたそうです。
また、梅干しのスッパさを思い、口にたまるツバで喉の渇きを癒したと言われています。